アライグマとタヌキの違いは?【尻尾の模様に注目】見分け方を覚えて適切な対処をしよう

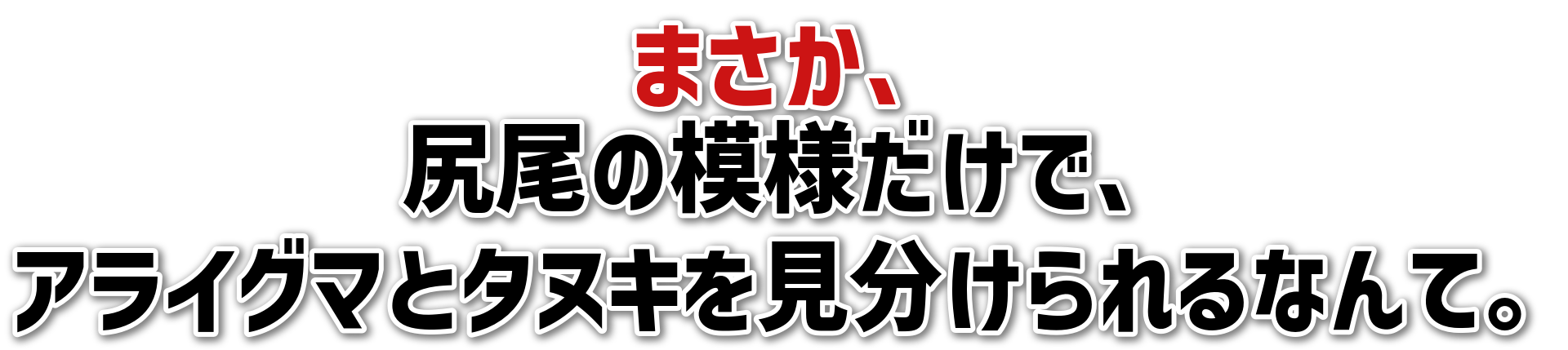
【この記事に書かれてあること】
アライグマとタヌキ、一見よく似た姿をしていますが、実は大きな違いがあるんです。- アライグマとタヌキの外見の違いを5つの特徴で解説
- 行動パターンの比較で両者の生態の違いを明確化
- アライグマ被害を見分けるポイントと効果的な撃退方法を紹介
- 足跡や尻尾の模様など、誰でも簡単に識別できるコツを伝授
- アライグマ対策に光と音を活用する簡単で効果的な方法を解説
見分け方を知らないと、大変なことに…。
アライグマは外来種で、家屋への侵入や農作物への被害が深刻。
一方、タヌキは日本の在来種で、比較的おとなしい性格。
この記事では、アライグマとタヌキの5つの特徴的な違いを詳しく解説します。
尻尾の模様や行動パターンなど、誰でも簡単に見分けられるポイントを押さえて、効果的な対策方法までご紹介。
これを読めば、あなたも野生動物の見分け名人に!
【もくじ】
アライグマとタヌキの外見の違い

体の大きさ比較!アライグマの方が大型
アライグマの方がタヌキより一回り大きいです。アライグマは体長50〜60センチ、体重5〜9キロと、かなりがっしりしています。
一方、タヌキは体長45〜55センチ、体重4〜8キロとやや小柄です。
「えっ、そんなに違うの?」と驚く方もいるかもしれません。
実際に見比べると、その差は一目瞭然です。
アライグマは中型犬くらいの大きさで、タヌキは小型犬サイズといったところでしょうか。
この体格差は生活環境の違いから来ています。
アライグマは木登りが得意で、力強い体つきが必要です。
一方、タヌキは地上で生活することが多く、身軽さが求められます。
体の大きさを見分けるコツは、以下の3点です。
- 全体的な印象:アライグマはごつごつ、タヌキはまんまる
- 頭の大きさ:アライグマの方が頭が大きい
- 足の長さ:アライグマの方が足が長い
確かにその通りです。
そんな時は、次に紹介する顔の特徴を見分けるポイントが役立ちますよ。
顔の特徴で見分ける!「マスク」vs「白目」
アライグマとタヌキの顔は、一目で見分けられるほど違います。アライグマの顔の特徴は「黒いマスク」、タヌキは「白い目の周り」です。
アライグマの顔を見ると、まるで泥棒のような黒いマスクが目立ちます。
「あれ?どこかで見たことあるな」と思った方、正解です!
アライグマのこの特徴的な顔は、漫画やアニメのキャラクターのモデルにもなっているんです。
一方、タヌキの顔は、まるでパンダのような白黒模様です。
目の周りが白く、頬に黒い模様があります。
「タヌキ顔」という言葉があるくらい、丸くてかわいらしい印象です。
顔の特徴を詳しく比較すると、こんな違いがあります。
- 目:アライグマは小さくて鋭い、タヌキは大きくてまん丸
- 鼻:アライグマは尖っている、タヌキは丸い
- 耳:アライグマは丸くて小さい、タヌキは大きくて三角
確かにその通りです。
そんな時は、次に紹介する尻尾の特徴が決め手になりますよ。
尻尾の模様に注目!縞模様vsふさふさ
アライグマとタヌキの尻尾は、まるで別の動物のようです。アライグマの尻尾は縞模様、タヌキの尻尾はふさふさです。
この違いは一目瞭然で、見間違えようがありません。
アライグマの尻尾は、まるでシマウマの模様を小さくしたような感じです。
黒と白の縞模様が5〜7本ほど交互に並んでいます。
「わー、おしゃれな尻尾だな」と思わず見とれてしまうかもしれません。
一方、タヌキの尻尾は、まるでふわふわの毛布のようです。
全体的に黒っぽい色で、とてもボリュームがあります。
「あったかそう〜」と思わず触りたくなるような、ふさふさ感があります。
尻尾の特徴をさらに詳しく比較すると、こんな違いがあります。
- 長さ:アライグマの方がやや短い
- 太さ:アライグマの方が全体的に太い
- 動き:アライグマは器用に動かす、タヌキはあまり動かさない
そんな時は、次に紹介する手足の特徴が見分けるポイントになりますよ。
手足の特徴!「器用な5本指」vs「4本指」
アライグマとタヌキの手足は、まるで別の生き物のようです。アライグマの手は「器用な5本指」、タヌキの手は「4本指」が特徴です。
この違いは、両者の生活様式を如実に表しています。
アライグマの手は、まるで小さな人間の手のようです。
5本の指がはっきりと分かれていて、とても器用に動かせます。
「えっ、本当に動物の手?」と驚くほど、物をつかんだり操作したりするのが上手なんです。
一方、タヌキの手は、典型的な犬科動物の足に近い形をしています。
4本の指があり、爪も鋭くありません。
「あれ?犬の足みたい」と思うかもしれません。
実際、タヌキは犬に近い仲間なんです。
手足の特徴をさらに詳しく比較すると、こんな違いがあります。
- 指の長さ:アライグマの方が長い
- 爪の形:アライグマは鋭く曲がっている、タヌキは短めでまっすぐ
- 足跡:アライグマは人間の赤ちゃんの手形のよう、タヌキは犬の足跡に似ている
そんな時は、次に紹介する毛並みの違いが重要なヒントになりますよ。
毛並みの違いに要注意!「粗い」vs「柔らかい」
アライグマとタヌキの毛並みは、まるで別の生き物のようです。アライグマの毛は「粗い」のに対し、タヌキの毛は「柔らかい」のが特徴です。
この違いは、両者の生活環境をよく反映しています。
アライグマの毛は、まるでワイヤーブラシのようにごわごわしています。
触ると「ちくちく」した感触があり、あまり気持ちよくありません。
この粗い毛は、木の枝をよじ登ったり、水辺で活動したりする生活に適しているんです。
一方、タヌキの毛は、まるでぬいぐるみのようにふわふわしています。
触ると「もふもふ」とした感触があり、思わず撫でたくなってしまいます。
この柔らかい毛は、地面の上で生活することが多いタヌキの生態に合っているんです。
毛並みの違いをさらに詳しく比較すると、こんな特徴があります。
- 色:アライグマは灰色がかった茶色、タヌキは黒っぽい茶色
- 密度:アライグマの方が毛が密集している
- 光沢:アライグマの毛はややつやがある、タヌキの毛は落ち着いた印象
確かにその通りです。
でも、これまで紹介した特徴を総合的に見ることで、アライグマとタヌキを見分けられる確率がぐっと上がりますよ。
これらの特徴を覚えておけば、「あれ?庭に何かいる!」と気づいた時、すぐに対処方法を考えられます。
アライグマなら要注意、タヌキならまだ安心、というように、適切な対応ができるようになるんです。
アライグマとタヌキの行動パターンを比較

活動時間帯の違い!夜行性vs薄明薄暮型
アライグマは完全な夜行性、タヌキは薄明薄暮型です。この違いを知ることで、効果的な対策が立てられます。
アライグマは、真っ暗な夜になると活動を始めます。
「カサカサ」「ガサガサ」と物音がし始めたら要注意。
深夜0時から明け方4時頃が最も活発になります。
「夜中に屋根裏からドタバタ音がするんだけど…」という相談、実はアライグマの可能性が高いんです。
一方、タヌキは夕方から夜明けにかけて活動します。
日没直後や夜明け前にも姿を見かけることがあります。
「夕方、庭に丸っこい影が…」なんて時はタヌキかもしれません。
この活動時間の違いは、両者の目の構造の違いから来ています。
アライグマの目は夜間視力に特化し、タヌキは薄暗い時間帯に適応しているんです。
対策のポイントは次の3つです。
- 深夜の物音にはアライグマを疑う
- 夕方や明け方の出没はタヌキの可能性を考える
- 夜間照明を活用し、アライグマの活動を抑制する
活動時間を知ることで、効果的な対策を立てられるんです。
例えば、アライグマ対策なら夜間センサーライトの設置が有効。
タヌキなら夕方の見回りを重点的に行うといった具合です。
木登り能力に大差!「得意」vs「不得意」
アライグマは木登りの達人、タヌキは木登りが苦手です。この違いを理解すると、被害予防や対策に大いに役立ちます。
アライグマの木登り能力は驚異的。
まるで猿のように、すいすいと木を登っていきます。
「えっ、あんな細い枝でも平気なの?」と思うような場所でも、バランスを取りながら器用に動き回るんです。
この能力を活かして、高い場所にある果実を狙ったり、屋根裏に侵入したりします。
一方、タヌキは地上生活が主。
木登りはあまり得意ではありません。
「ふわふわした見た目なのに、意外と不器用なんだな」と思うかもしれません。
タヌキは主に地面や低い位置にある食べ物を探します。
この木登り能力の差は、両者の体の構造の違いから来ています。
アライグマは鋭い爪と器用な手先を持ち、尻尾でバランスを取ります。
タヌキはそこまで発達した爪や手先の器用さがないんです。
対策のポイントは以下の3つです。
- 果樹園では、高い位置の果実もアライグマの被害に注意
- 屋根や2階以上の窓からの侵入はアライグマを疑う
- 地上レベルの対策だけでなく、高所の侵入経路もチェック
アライグマは建物の壁を伝って屋根に登ることもあるんです。
木登り能力の違いを知ることで、より効果的な対策が立てられます。
高所からの侵入を防ぐことが、アライグマ対策の重要なポイントになるわけです。
水辺での行動!「水遊び好き」vs「飲水程度」
アライグマは水遊びが大好き、タヌキは水辺で主に飲水をする程度です。この違いを知ると、庭や周辺環境での対策に役立ちます。
アライグマは、まるで子供のように水遊びを楽しみます。
「ジャバジャバ」「ピチャピチャ」と水音がすれば要注意。
手を使って食べ物を洗う習性があり、水辺で餌を探すのも得意です。
池や小川があれば、そこで小魚や貝を探して食べることも。
「えっ、うちの鯉が減ってる!」なんて被害も、実はアライグマの仕業かもしれません。
一方、タヌキは水辺では主に飲水をする程度。
水遊びをしたり、水中で餌を探したりすることはあまりありません。
「タヌキさん、意外とおとなしいんだな」と思うかもしれませんね。
この水辺での行動の違いは、両者の進化の過程で身につけた生存戦略の違いから来ています。
アライグマは北米原産で、河川や湖沼の多い環境に適応してきました。
タヌキは森林や草原を中心に進化してきたんです。
対策のポイントは次の3つです。
- 庭の池や水鉢はアライグマの餌場になる可能性がある
- 夜間に水音がすれば、アライグマの存在を疑う
- 水辺の足跡や糞の有無をチェックし、アライグマの痕跡を探す
実は、ペットの水飲み場や雨水がたまった場所でも、アライグマは水遊びをすることがあるんです。
水辺での行動の違いを理解することで、庭や周辺環境でのアライグマの存在に早く気づくことができます。
これが効果的な対策の第一歩になるんです。
人間への警戒心!「大胆」vs「臆病」
アライグマは人間に対して大胆、タヌキは臆病です。この性格の違いを知ることで、遭遇時の対応や予防策が変わってきます。
アライグマは、人間を見ても平気な顔をしていることが多いんです。
「あれ?私のこと全然怖がってない?」なんて思うほど。
好奇心旺盛で、人間の生活圏内に積極的に入り込んできます。
ゴミ箱をあさったり、ペットフードを盗んだり。
時には人間に向かって威嚇することさえあるんです。
一方、タヌキは人間を見るとすぐに逃げ出します。
「あ、タヌキだ!」と思った瞬間には、もうサッと姿を消しているかもしれません。
人間との接触を極力避けようとする、慎重な性格なんです。
この警戒心の違いは、両者の生態と歴史的背景から来ています。
アライグマは北米原産の外来種で、人間との接触に慣れています。
タヌキは日本の在来種で、長年人間を恐れる習性が身についているんです。
対策のポイントは以下の3つです。
- 人を恐れずに近づいてくる動物は、アライグマの可能性が高い
- アライグマに遭遇したら、絶対に餌を与えない
- タヌキは逃げるので、追いかけたり脅かしたりしない
むしろ、人を恐れないからこそ注意が必要なんです。
餌付けは絶対にNG。
一度人間を餌の供給源と認識すると、どんどん大胆になっていきます。
人間への警戒心の違いを理解することで、適切な対応ができるようになります。
アライグマには毅然とした態度で接し、タヌキには優しく見守る。
こんな対応の使い分けが、人と野生動物の共存には大切なんです。
食性の違い!「肉食傾向」vs「雑食性」
アライグマは肉食傾向が強い雑食性、タヌキは植物質も多く食べる雑食性です。この食性の違いを理解すると、被害の予測や対策に役立ちます。
アライグマは、まるで小さな肉食獣のような食生活。
「ガリガリ」「ボリボリ」と肉を食べる音が聞こえてきそうです。
魚や小動物、昆虫などのタンパク質を好んで食べます。
もちろん果物や野菜も食べますが、肉食傾向が強いんです。
「えっ、うちの庭の小動物がいなくなった?」そう、アライグマの仕業かもしれません。
一方、タヌキはより幅広い食性。
果実や木の実、草、昆虫などをバランスよく食べます。
「タヌキさん、意外と健康的な食生活だな」と思うかもしれませんね。
肉も食べますが、アライグマほど積極的ではありません。
この食性の違いは、両者の消化器系の構造と進化の過程から来ています。
アライグマはより肉食に適した消化器系を持ち、タヌキは植物質も効率よく消化できる構造になっているんです。
対策のポイントは次の3つです。
- ペットフードや魚の残り物は、アライグマを引き寄せる可能性が高い
- 果樹園では、アライグマもタヌキも被害をもたらす可能性がある
- 小動物の不自然な減少は、アライグマの存在を疑う理由になる
実は、人間の食べ物の残りやゴミもアライグマの格好の餌になるんです。
食性の違いを知ることで、どんな場所にアライグマやタヌキが来る可能性があるか、予測できるようになります。
例えば、ゴミ置き場の管理を徹底したり、果樹園にはネットを張ったり。
食性に合わせた対策を立てることで、より効果的にアライグマやタヌキの被害を防ぐことができるんです。
アライグマ被害を見分け撃退する5つの方法

足跡チェック!5本指vs4本指の跡を確認
アライグマとタヌキの足跡は、指の数で簡単に見分けられます。この違いを知れば、どちらが庭に来ているのか一目瞭然です。
アライグマの足跡は、まるで小さな人間の手形のよう。
なんと5本指がくっきりと残るんです。
「えっ、動物なのに5本指?」と驚く方もいるでしょう。
そう、アライグマの手は驚くほど人間に似ているんです。
一方、タヌキの足跡は4本指。
犬の足跡に似ていて、丸っこい形をしています。
「ああ、これなら見たことある!」という方も多いのではないでしょうか。
足跡を見分けるコツは、次の3つです。
- 指の数:アライグマは5本、タヌキは4本
- 足跡の形:アライグマは細長い、タヌキは丸い
- 爪の跡:アライグマははっきり残る、タヌキは薄い
実は、ちょっとした工夫で足跡を確認できるんです。
例えば、庭の一角に細かい砂を敷いておくとか、雨上がりの柔らかい土の上を観察するとか。
こんな裏技も。
夜、庭に小麦粉を薄く撒いておくんです。
翌朝、そこに残った足跡を確認すれば、どちらが来ていたかすぐにわかります。
「なるほど、探偵みたいだな」とワクワクしてきませんか?
足跡を見つけたら、スマートフォンで写真を撮っておくのもおすすめです。
「これってアライグマ?タヌキ?」と友達に相談するのも楽しいかもしれません。
足跡チェックで、あなたも野生動物の達人になれるんです。
ゴミ箱の荒らし方!「器用」vs「乱雑」
アライグマとタヌキ、どちらがゴミ箱を荒らしたのか、その痕跡で見分けられます。荒らし方の違いを知れば、対策の立て方が変わってきますよ。
アライグマのゴミ荒らしは、まるで泥棒のよう。
器用な手先を使って、ゴミ箱のフタをすいすいと開けちゃうんです。
「えっ、こんなに難しいフタも開けられるの?」と驚くほど。
中身を選り好みして食べ、残りはきれいに脇に寄せてあったりします。
まるで「いただきま〜す」って感じですね。
一方、タヌキのゴミ荒らしは乱暴。
ゴミ箱をひっくり返して、中身を散らかし放題。
「まるで台風が来たみたい!」と思うほどです。
タヌキは手先が不器用なので、力任せに荒らすんです。
ゴミ箱の荒らし方を見分けるポイントは、次の3つです。
- フタの開け方:アライグマは丁寧、タヌキは力任せ
- 中身の散らかり具合:アライグマは選択的、タヌキは無差別
- 食べ残しの状態:アライグマは整然、タヌキは乱雑
アライグマなら、フタをしっかり固定する対策を。
タヌキなら、ゴミ箱自体を安定させる工夫が必要です。
ゴミ箱対策の裏技、こんなのはどうでしょう。
ゴミ箱の周りに砂を撒いておいて、足跡をチェック。
または、ゴミ箱にカメラを設置して、夜の訪問者を撮影。
「まるで野生動物ドキュメンタリーの撮影みたい!」なんて、ちょっとワクワクしませんか?
ゴミ箱の荒らし方を見分けることで、適切な対策が立てられます。
これで、朝起きたときのゴミ散らかし被害とはおさらばです。
果樹園被害!「実だけ食べる」vs「枝ごと折る」
果樹園での被害も、アライグマとタヌキでは大きく異なります。その違いを知れば、どちらが犯人なのかすぐにわかりますよ。
アライグマの果樹被害は、まるでグルメ。
熟した実だけを器用に摘み取って食べるんです。
「まるで人間みたい!」と驚くほど上手に食べます。
木に登る能力が高いので、高い場所の実もお構いなし。
枝を折ることはほとんどありません。
一方、タヌキの果樹被害は乱暴そのもの。
地面近くの実を食べるときに、枝ごと折ってしまうことが多いんです。
「えー、そんなに力持ち?」と思うかもしれませんが、タヌキは木登りが苦手なので、地上から手の届く範囲で荒っぽく食べるんです。
果樹被害を見分けるポイントは、次の3つです。
- 被害の高さ:アライグマは高所まで、タヌキは地面近く
- 実の食べ方:アライグマは丁寧、タヌキは乱暴
- 枝の状態:アライグマはそのまま、タヌキは折れている
アライグマなら木全体の保護が必要ですが、タヌキなら下部だけ重点的に守れば良いでしょう。
果樹被害対策の裏技、こんなのはどうでしょう。
木の周りに砂を撒いて足跡をチェック。
または、低い位置に風鈴を付けて、音で接近を察知。
「おっ、なんだか忍者屋敷みたいだな」なんて、ちょっと楽しくなりませんか?
果樹被害の特徴を見分けることで、効果的な対策が立てられます。
これで、大切に育てた果実を守れるはずです。
がんばって対策を立てて、美味しい実をたくさん収穫しましょう!
屋根裏の音!「コツコツ」vs「ガサガサ」
屋根裏から聞こえる音でも、アライグマとタヌキを見分けられます。その違いを知れば、どちらが住み着いているのか、耳で判断できるようになりますよ。
アライグマの屋根裏での音は、「コツコツ」「カチカチ」といった規則的な音。
まるで小さな職人さんが作業しているみたい。
器用な手先を使って、あちこち探り回る音なんです。
「えっ、そんなに規則正しいの?」と驚く方もいるでしょう。
そう、アライグマは非常に几帳面な性格なんです。
一方、タヌキの屋根裏での音は「ガサガサ」「ドタバタ」といった不規則な音。
まるで子供が走り回っているよう。
タヌキは動きがぎこちないので、体全体を使って動き回るんです。
「うわー、屋根が落ちそう!」と心配になるほど大きな音を立てることも。
屋根裏の音を見分けるポイントは、次の3つです。
- 音の規則性:アライグマは規則的、タヌキは不規則
- 音の大きさ:アライグマは小さめ、タヌキは大きめ
- 音の継続時間:アライグマは長時間、タヌキは短時間
アライグマなら小さな侵入口を探して塞ぐ必要がありますが、タヌキなら大きな穴や隙間を重点的にチェックしましょう。
屋根裏対策の裏技、こんなのはどうでしょう。
屋根裏に録音機を仕掛けて、夜の音を記録する。
または、赤外線カメラを設置して、暗闇での動きを撮影。
「おお、まるで怪奇現象調査隊みたいだな」なんて、ちょっとスリル満点ですね。
屋根裏の音の特徴を見分けることで、適切な対策が立てられます。
これで、夜中の不気味な音とはおさらば。
ぐっすり眠れる日々が戻ってくるはずです。
撃退には「光と音」が効果的!簡単対策法
アライグマもタヌキも、「光と音」が苦手です。この特性を利用した対策で、両方とも効果的に撃退できますよ。
まず光による対策。
突然の明るい光は、夜行性のアライグマにとって大敵。
センサー式のライトを設置すると、近づいただけで明るく照らされて逃げ出します。
「まるで舞台のスポットライトみたい!」と思うほど効果的。
タヌキも光が苦手なので、同じように効果があります。
次に音による対策。
大きな音や突然の音は、両方の動物を驚かせます。
風鈴やラジオなどの人工的な音を使うと良いでしょう。
「えっ、こんな簡単なもので効果あるの?」と驚く方もいるかもしれません。
でも、野生動物にとって人工音は非常に不快なんです。
効果的な「光と音」の使い方、3つのポイントがあります。
- タイミング:動物が活動し始める日没直後に開始
- 場所:侵入されやすい場所を重点的に
- 組み合わせ:光と音を同時に使うとさらに効果的
人の耳には聞こえにくい高周波音を出す装置もあるんです。
また、ピンポイントで光を当てる機器を使えば、周囲に迷惑をかけることなく対策できます。
撃退の裏技、こんなのはどうでしょう。
ペットボトルに水を入れて庭に置く。
光を反射して動物を驚かせる効果があります。
または、アルミホイルで作った風車を立てる。
風で回ると光と音の両方で撃退できます。
「へえ、子供の自由研究みたいで楽しそう!」なんて、家族で対策を考えるのも良いかもしれません。
「光と音」を上手に使えば、アライグマもタヌキも効果的に撃退できます。
これで、庭や家の周りの小動物被害とはさようなら。
安心して暮らせる日々が戻ってくるはずです。
さあ、今日から「光と音」作戦の始まりです!